主人の会社に学生時代にアルバイトにおいでになったこともある横山さん、伺ってみようとおもいます。
 ブログ最新記事
ブログ最新記事戸塚久美子後援会事務所
-
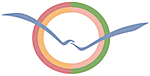
戸塚久美子後援会のマークです。
女性・水のW、コラボレーションや茶、チャイルド、コミュニティーなどのCの文字の重なりで円です。「文化の融合」がテーマです。
県民の多くが、見守っていた結果です。県議会への失望は広がっています。私にそういう声が届くからです。
条例が不備が多いのならば、受理する前に、すり合わせをして最低限の直しをその時にして、議会審議に値するまでのものを受け付ける方がよかったのでしょう。結局入口の議論で終わってしまったからそう思ったのです。
修正案は有志の皆様が努力されて、せっかく修正出来たのにもったいないことです。その案には、只今の中電の防潮堤工事が終わり、その安全性や、その他の全ての安全性が構築できた暁に、また国が再稼働をさせるとなった時に住民投票する。たしかそのような案だったと思いますが、3連動の地震のこともあり、浜岡の再稼働は当分向こうになるでしょうし、あるとしても、日本中で一番最後の再稼働要請があるかないか。
その時に住民投票でもよかったのだと思います。それが修正案でした。
時代が進めば、畜電池システムももっと安価にできるでしょう。スマートグリット等の新しい技術もどんどん出てきます。
もう少し時間を掛けて考えてもよいのかもしれません。
しかし、県民の声に応えられなかった県議会の姿勢には問題を感じます。どうして「決議」をしなかったのでしょう。再稼働への縛りをつくるのも1つの方法です。
そうすれば、市民団体も少しは面目がたちますし、議会の踏み込んだ姿勢も見て頂けたのではないでしょうか?
正しい知見が取りにくい原子関連。
中部電力管内は、電力会社の先見性があってベストミックスで、発電がおこなわれています。原子力の割合が10数%であり、火力発電所もつくられたので、安定供給を頂いています。
自然エネルギー、再生可能エネルギーなどの連携等を合わせて、電力会社とは話し合いをしていきたいものです。
はじめての企画を準備しています。招待客10席と一般のチケットを求めて頂く御席40席、合わせて50席と頂きました。
ピアノは、新進気鋭の掛川出身の佐藤元洋さん。楽しみです。
私達の準備も始めていて、海外のインストラクターへメールにてそれぞれの国の水事情など問い合わせています。インストラクションもお楽しみに。
午後大東図書館にて、13時から
私はボランティア会員になりました。 実質「読み聞かせ」「出前講座」「留学生受け入れ」など松本亀次郎先生の偉業を継続的に市民で伝える活動をする方が好きですから。
ブログにも書きましたが、浜岡原発の県民投票関連の議案上程を傍聴したいと考えて出掛けましたが、調査も2つ程、先輩議員にお願いしながらして参りました。1つは小児の慢性特定疾患の医療機関にかかる上での不都合を改善する制度改正を考えているか否か。もう1つは、家庭医養成への支援体制が見えないので、その辺りを伺い、また後日先輩議員から説明を受けることになっています。場合によっては国会議員をお願いして法整備も必要なのかもしれません。
こういう仕事していると楽しいです。知らないことが分かったり、解決の糸口が見つかったり、方程式が解けるようですね。市民活動家は社会貢献してこそ市民活動家ですから。
昨日の学習は、商工会議所青年部の皆様の学習会のようですが、一般の者も入れてくださいます。シズテツストアの社長中村様の講演でした。ものすごいパワーです。
目的を社員と共有することはもちろん、社会貢献を考えないでお客様と接することなどできないと言わんばかりの御教示に一々納得。拝聴できたことを感謝します。
私が市議会時代、自治基本条例制定を提案させて頂いたおりには、わがまちには「生涯学習理念があるから基本条例はいらない」という市の幹部の意見を聞いたことがありました。
それでもあまりにも住民自治がやりにくいので「条例を制定」を求めました。北海道ニセコにはじまり全国何処のまちでもすでに条例化されているのですから。何年間か掛川市でも議論をしてくれました。関わった皆様に感謝しています。もう少しで議会上程ということも聞いています。
しかし、言葉は浸透しているようにこの頃感じますが、何故この条例が必要か、この条例が果たす役割など、まだまだ浸透していないことに気づかされました。
地域で意見を集約して地域の方針を市や県へ伝えて行くときのプロセスの中で、地域で問題が発生してしまいます。それを絶対避けるようにと考えて、区長会とまちづくり協議会との協働体制や情報の共有化に努めるのですが、最初は円滑にスタートしても、1年や2年経ちますと区長様方が入れ替わります。そうなりますと「聞いていない、もっとこういう組織の方がよかったんじゃないか・・」「それは住民の総意ではない」など出るわ出るわ疑問の数々。苦労して地域の意見集約を市役所や県の専門的な職員らを交えて導きだす様々な学習を繰り返している方々にとっては、最初に戻られるのはかなりの負担です。
聞こえた情報では、ある地区では新たな区長会が、それ以前の区長会の時代に発足したまちづくり委員会を解散させてしまったということも聞こえてきました。何か事情があったのでしょうが残念なことです。
地域自治は、区長様方がリーダーですが、わずかな人数では地域の課題全般にはなかなか対応しきれません。河川愛護、人口増加策、商店街活性化、有害鳥獣から農地をまもる、道路の改良を10年のスパンで要請していく、高齢者の皆様へ介護を受けなくてもよい地域の支援活動、子供たちへの青少年育成事業、などなどわずかの例に挙げても1年2年に出来るものはありません。区長会の交代は2年ほどです。せめて10年できる専門をもつ活動組織が地域の中にほしいものです。
行政だけにはお任せできない時代です。行政改革で行政マンの数も減りました。予算もありません。私達地域が取り組むことで、地域の実情が一番分かった私達の方が「かゆい所に手が届く」適性なる意見集約と税金投入の最適化が出来るはずです。
ほんの行き違い、ほんの感情的なもので、地域が取り組んできたことがご破算になってしまうのは残念です。行政も地域の力の「強さ」と「もろさ」の双方あることを理解して、自治基本条例の制定における環境を今一度見直してほしいものだと期待申し上げるものです。
人間は思考で行動を決めるより、感情で行動を決める方が多いと先日ある講演会で聞いたことがあります。条例は思考的です。感情をも納得させるテクニックがいるようです。
私は市議時代から県道の改良に同志の皆様と「協働による道づくり」の手法で何路線も関わってきました。しかし、県道1本だけの整備方針を導いてきただけです。この7月8月のほとんどの時間をつかって、取り組んでまとめた今回の事例は「通学路に視点を当てて、県道、市道、都市計画道路、鉄道の4つの交通が絡むエリアの道路問題」であり、厳しい活動でしたが、足掛け4年のまとめを皆さんとしています。地域の皆様の子供達を思う気持ちの熱いものは素晴らしいです。
まだ地域内の読み合わせや修正が終わっていませんが、最終目的は「子供の命を守る」ことであるので、皆さんのご理解は進むものと信じています。
厳しい活動で、苦しみましたが、視点を変えれば今思えば私自身も大変勉強になりました。
この活動には、予算が何処からも尽きませんでした。だって市道だけの問題じゃない、県道だけの問題じゃない、どこも責任者にはなれないのですから。
でもこういうエリアや問題を抱えているところは氷山の一角なのかもしれませんね。
地域住民が導きだした整備方針を今後提言するわけですが、これは大変重いものであり、全国の通学路問題を扱うモデルになるはずです。近いうちに県の協働の底力組の友人達にも話してみたいと思っています。
朝6時に集合です。参加したい方はNPOスローライフへお問い合わせください。