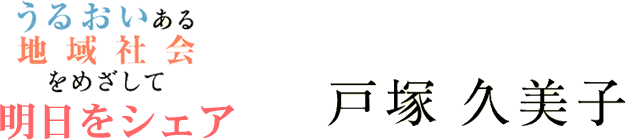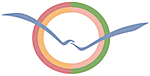1958年静岡市生まれ。
静岡雙葉高等学校、文化女子大学家政学部生活造形学科(織物専攻)卒。
1988年に結婚、掛川市が本籍地となり、1995年、掛川市に転入(横浜市より)。
日々の暮らしを平凡に営むが、嫁いだ地域の水の問題がつながり、政治の世界へ。
旧掛川市議会議員(2003年4月~2005年3月)
掛川市議会議員 (2005年4月~2009年4月)
静岡県議会議員 (2009年7月~2011年4月)
家族:夫、長女
- 元掛川市民生委員・児童委員・主任児童委員
- 元掛川市環境創生委員
- 元掛川市女性行動計画推進委員
- 元太田川流域委員
- 元倉真川河川改修勉強会事務局
- 第二回世界お茶まつり(2004年)準備実行委員
- 静岡県茶文化振興協会元理事(2005年3月まで)
- NPO法人日本茶インストラクター協会元理事(2005年3月まで1期)
- 静岡県「強い農業づくり交付金事業」評価委員(2009年3月まで)
- NPO法人日本茶インストラクター協会理事(2011年3月から3期)
- 倉真地区まちづくり委員会 顧問
- 中東遠総合医療センター 病院ボランティア設置検討委員(2011)
- 掛川地区更生保護女性会会長(2013.5~2015.5)
- さくら音楽祭(第一回)実行委員長(2014.3)
- NPO 人とペットの暮らしを育む会 ナームハート 理事・事務局長(2014・3~2020・10月解散)
- 日本茶AWARD2014 実行委員(2013.12~)
- NPO法人 冀北の杜 理事長(2015・8~)
- 障がい者就労継続支援B型事業所 きほくのもり☆ペンタス 設置者
- (一社)倉真報徳社 副理事長(2016・1~)
- 障がい者就労継続支援B型事業所
きほくのもり★ペンタス理事長(2016・4~) - NPO法人日本茶インストラクター協会理事(2018・3~1期)
- SHIZUOKA TEA WEEK第1回実行委員長
- (公社)大日本報徳社 理事 (2020・4~)
- 掛川市地区 保護司 (2020・⒒~)
- その他
掛川地区更生保護女性会、掛川市子どもの読書活動を考える会、fan地域医療を考える会、NPO法人掛川市民オーケストラ等 会員
私のスタイル
 社会生活の最小単位は家族です。その家族を大事にすることが、市や県や国のことも大事に考えられるベースとなると私は信じます。
社会生活の最小単位は家族です。その家族を大事にすることが、市や県や国のことも大事に考えられるベースとなると私は信じます。議員生活と、子育て・介護を両立していく過程が、そのままワークライフバランス(仕事と生活の調和)について考える機会となりました。
日々の生活の中で、暮らしの細やかな疑問や課題を放っておかないで、ひとつひとつ着実に行動することで解決していく。それは、これまで私を形づくってくれた「織物」という手仕事を通じて、また「茶の世界」を通じて培われた、私のスタイルなのかもしれません。感性と実践力をもって、社会に奉仕する女性として、活動を促進していきます。
「本気ですれば大抵のことはできる。
本気ですれば何でも面白い。
本気でしていると誰かが助けてくれる。
人間を幸福にする為に本気で働いている人間は、みんな幸福でみんなえらい」
(明治大正時代の教育者、後藤静香の言葉より)
何事にも興味を持って、「本気」でまい進していくのが私のスタイルです。