菊川市のアエル大ホールで開催されます。毎年の開催ですが、駐車場がいつもいっぱいです。お早目にお出かけください。初代タイガーマスク佐山サトル氏の講演もあります。
 ブログ最新記事
ブログ最新記事戸塚久美子後援会事務所
-
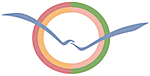
戸塚久美子後援会のマークです。
女性・水のW、コラボレーションや茶、チャイルド、コミュニティーなどのCの文字の重なりで円です。「文化の融合」がテーマです。
菊川市のアエル大ホールで開催されます。毎年の開催ですが、駐車場がいつもいっぱいです。お早目にお出かけください。初代タイガーマスク佐山サトル氏の講演もあります。
「新結合」どこかで聞いたことが。県知事がその職つつかれた直後、よく聞いた言葉です。そして「シュンペーター」も。
アベノミクスの3本目の矢は、成長戦略であるが、イノベーションによる新結合なしには実現は難しいだろうと講師は言われます。
「楽天」の三木谷会長兼社長の講演を拝聴しました。私が参加した東京で行われる全国月例会では最多の参加者だったのでは?と思うほど大勢。1200人がいました。すごい!
創業は7人から、今では1万人の社員が。社内後は英語で、TOEIC526点平均が2年で734点へ、社内平均が200点も上がっていて、新入社員は830点以上を求めているようです。社員一人一人がグローバルな思考に変わってきているといわれます。
そして創業から一貫してミッションは「エンパワメント」。
その素地ができた中で、シュンペーターの新結合を誘導しようとしています。新しい商品・新しい生産方式・新しい市場・新しい原材料の供給源・新しい組織の5つの新結合。
国境はなくなるといわれます。インターネットの可能性で世界は大きな社会を形成しグローバル化へ。サービスと物のでは、国境がなくなるのであれば、それでは国内での残るものは何だろう?
それは、人間そのものが生産する「感動」=文化・芸術にかかるもの、ストーリーのあるもの・ことであるのではないか?と考察し、「ジャパン・アゲイン」には市場経済とアイデンティティーのはざまで起こる相当な議論も必要なのだろうと感覚的な考察をしました。
ため池の改修工事を記念し、農業者だけではなく、地域で守り育む農業資源のため池になるために、みんなで憩う花いっぱいの散歩道を創ります。初めの一歩です。
時間は午後1時30分から。場所は倉真3区里在家です。
25人の大人と13人の子供たちと70~80本の紫陽花の苗を植えました。
第3弾 沖之須防災林・森の防波堤づくり植樹祭が開催されます。
600人の予定が1200人という大勢の皆さんがお集まりくださいました。
主催者は東日本大震災を支援掛川市民の会。セレモニーとコンサート、募金。
分け合うパンもすべて売り切れました。311円であるにかかわらず、寄付といって500円も1000円もしてくださる市民の皆様、本当にありがとうございました。
韓国も日本も世界的に低いレベルを争う「女性の登用の低い国です。確か、100番台だったと思います。
今日は、女性大統領が誕生したお隣の韓国。儒教の国であり、日本以上に女性の登用が遅れていた国であったの韓国が、日本より先に政治の首長を女性にされました。
すごいです。
議会議員の定数に「クオータ」制度を取り入れて、一定の女性議員を故意に確保する政策を推進した結果が今日を迎えているのかもしれません。
日本でも政党で、そのような数の調整をしているところもありますが、地方都市の議会であっても考えていくべきことでしょう。
先日の「女性農業者の集い」に伺った時も、クオータ制度さえあれば、この会場の女性たちのリーダーは市議になっていただける資質十分なのにと心の中でつぶやいていました。
掛川市には女性議員はいないのですが賢い女性たちは大勢おられるのです。
自民党政権になってよい景気になりつつあるようで、よろしいですね。日本には冷戦時代のベルリンの壁崩壊からイデオロギーの論争はほとんどなく、憲法にある国民主権の「民主」、民主主義における自由経済路線は民主党であっても自民党であっても同じですね。
それにしてもアメリカとの外交やTPPのことでも、それを裏で支える官僚の活躍が推察されて、本当に民主党になかった手腕を見せていただいています。民主党はアメリカにも官僚にも愛されなかったのですね。(こんな簡単な言葉で表現できる問題ではありませんが、、)
アベノミクスも好調で株は上がり、円は安くなって輸出関連企業の経営は素晴らしい利益を創出。私たちが危惧していた金融緩和はこれでよろしいのでしょうか?小泉内閣時代の景気成長期にも2%の物価上昇にはならなかった日本が、2%を実現するには巨大な緩和が必要なのでしょう。円は100円を超えてしまうかもしれません。ガソリンや食料の値上がりは確実に生活に入ってきました。
17日の経済新聞の日曜日に考えるの中で、「アベノミクスの死角は」というテーマで記者に答えているマーティン・フェルドシュタイン氏(ハーバード大学教授)のインタビュー記事がありました。一番心配されていることはアベノミクスの先には、長期の金利上昇があって、財政再建を阻むと指摘されていました。~今でも財政破たんしているという方々がおられるのに?~
日銀の新しい総裁も決まります。少子高齢社会の日本の経済運営は世界中の興味の的でしょう。この金融政策は本当に私たちの国を強いものにするのか?よく見せていただきたいと思っています。世界で初めてする金利を上げない金融緩和政策ができるのか。私たちは、経済学のライブでの学習が始まります。
あるところでは、25年度農業土木予算が、補正でその財源が確保されて、25年度分の予算の使い道を探しているという冗談のような話が聞こえてきます。
緊縮財政や、農家個別補償制度創設で、農業土木予算は激減していた中で、新たな農業創出のためのハードの在り方を模索していた矢先、大きな予算が転がり込んできたわけです。
また、行政職員も、事業を受託する業者も人員削減で、仕事量に見合う人材の確保には困惑の声が。とても残念な環境下での大型予算振舞いです。
この状況に、たまりかねた、元総務相を務められた片山善博慶大教授が新聞の特集に「公共事業と地域経済・先祖返りの印象拭えず」という論評を書かれていました。
さらにグランドワーク三島の「ジャンボ渡辺」さん、渡辺豊博氏も新聞紙上に苦言?提言?を書かれていました。
地方分権社会を地方で踏ん張って創造しようとしていた私たちは、予算をいただけるありがたさと、困惑の交錯した複雑な心境です。