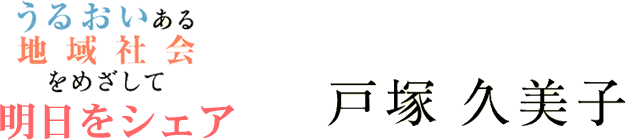1987年6月30日、第4次全国総合開発計画(俗に第4全総)が閣議決定されて、「第2東名自動車道路構想」が実施されることに。法定の路線名は、「第二東海自動車道路横浜名古屋線」と言うのだそうです。1989年2月には基本計画が公示され、1993年12月には長泉沼津~豊田東JCTの工事が着手されました。平成5年ですから、その頃道路用地買収価格が世間を騒がせていましたね。来年が来れば20年も前の話になりますね。
2006年には日本道路公団民営化、中日本高速道路株式会社が事業を引き継ぎ、6車線を暫定4車線でと言うことも決まりました。2012年4月14日開通は162㎞。2020年に全線253.2㎞開通予定で総事業費7兆円とのこと。
設計速度は140㌔、でも3年もかけた議論の結論は規制速度100㌔となりました。静岡県は今後、6車線化を前提に法定速度を140㌔を国へ要望していくのだそうです。
以上の様な歴史や概要は、皆さんもネット上ですぐに探せますが、あまり探せない情報としては、①トンネル工事の技術、②破砕帯の湧水などを少しご紹介。
①新東名上の最長トンネルの「粟ヶ岳トンネル」は工事中は「金谷トンネル」と言っていましたが、TBM(トンネルボーリングマシーン)の活用ほかで、脆弱な地盤の山岳トンネルの工事技術が評価されて、平成19年度の土木学会技術賞受賞。
②湧水との戦いも、映画「黒部の太陽」で有名な黒4ダムの破砕帯からの湧水は660l/h、粟ヶ岳は400l/hであり、大変厳しいものであったこともわかりました。地元の水源枯渇は当たり前の事象だったのでしょう。
橋梁の数、トンネルの数も夥しいものです。きりがない程の情報が満載な新東名です。
工事で命をなくされた方も大勢おられるでしょう。物故者の冥福を祈りつつ、国家プロジェクトに携わった方々に御礼を申し上げたいと思います。
 ブログ最新記事
ブログ最新記事戸塚久美子後援会事務所
-
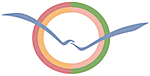
戸塚久美子後援会のマークです。
女性・水のW、コラボレーションや茶、チャイルド、コミュニティーなどのCの文字の重なりで円です。「文化の融合」がテーマです。