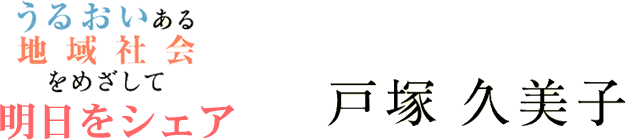この報告が休止していて申し訳ありません。
書きたいことがあっても、時期を逸してしまって、、、あ、そうそう過日市内で講演会での鷲山先生のサーバントリーダーのお話はすごく響きました。・書くのを忘れてしまいました。
今日は書きたいことは、なぜに横浜で、婦人会がいち早く婦人会館も建設して活動を活発に展開できたかです。関東大震災の被災地を婦人たちは下支えしていました。
シティガイドの嶋田さんに伺ったことをまとめると、その「なぜ」には2つの理由があるようです。
1つは、横浜が空気の流れが自由で、多様性を認める社会環境であったこと。
江戸時代末期まで横浜は皆様ご存知のように貧しい漁村。家も100戸ほど。武士のいない町。ペリー来航で一転。武士は初めからいなく、貿易の中心地となり商人のまちへ。他の都市とは逆で、高等学校も商業学校の設立が早い。縦社会ではなく横つながりの社会で、空気の流れが自由であったこと。
2つ目は、子女の教育環境が整っていて、関東大震災のころには、高等教育を受けた婦人たちが大勢いたまちであったこと。外国人居留地となって、ミッションスクールができて、子女の教育は明治初期から行われていましたから、教育を受けた婦人たちは他の都市に比べれば大勢いたに違いありません。
裕福な商家の婦人達が、家業から持ち出しの寄付金を当てにするのではなく、10銭募金をしながら婦人会館を建て活動の拠点を作ったようです。ミッションスクールの博愛精神そのものです。
時代が少し進み、広島出身の女性市議会議員はこういわれたそうです。「私は広島にいたら市議会議員になってはいなく、なろうとも思わなかった、横浜だから市議会議員になれたのだ」と。
女性の社会進出の環境整備に参考になることに出会え、有難く、講師の嶋田先生に感謝いたします。
 ブログ最新記事
ブログ最新記事戸塚久美子後援会事務所
-
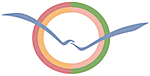
戸塚久美子後援会のマークです。
女性・水のW、コラボレーションや茶、チャイルド、コミュニティーなどのCの文字の重なりで円です。「文化の融合」がテーマです。